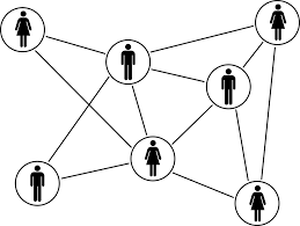挑戦することについて
今受験シーズン真っ只中。今回は「挑戦」について考えてみました。
誰もがいろんな分野で、難易度も様々な挑戦を一度は経験したことがあると思います。
私も今まさに人生で数回しかない大きな挑戦をしています。
それも重なってこのお題について考えてみたくなりました、
そもそも「挑戦」とは、いろんな捉え方があると思いますが、調べてみると
「目標達成や自己成長のために、困難やリスクを伴う新しい行動や経験に
立ち向かうことです。」
という回答がでます。
目標達成は思いつきますが、自己成長のためにというところに、「おーっ」と思いました
自己成長のために困難や、リスクを伴う新しい行動や景観をするというのは、
普通に生活していく上では、メリット、デメリットを天秤にかけてしまいそうになると思います
多くの人は自己成長を考えていても、リスクがあるならノーリスクの安全側、困難が伴うなら、
より少ない方と考えてしまいがちだからです
挑戦することのメリット、デメリットって何だろうと改めて考えてみると
メリットとしては、新しい知見や、スキルを習得して能力向上が可能、経験を通して視野が
広がり新たな発見や出会いが期待できるなどの自己成長でしょうか
さらに、自分の限界に挑むことで、新たな可能性を見い出せたり、成功体験を積み重ねて、
自己肯定感が高まるなどです
では逆にデメリットは挑戦には失敗がつきもので、目標達成ができない可能性がある
また失敗した場合、時間や労力を無駄にしてしまうことがあって、その恐れが、挑戦を
躊躇させる原因となることもあるでしょう
時には精神的、時間的、経済的な負担がかかることもあって、挑戦を諦めることにも
繋がりかねます
両方ともこの他にもありますが、特に大きな影響を与えていると思います
挑戦する上で大切なことは、目標設定や、計画性、リスク管理、心の準備、周囲の
サポート体制があると思います
スマホの開発、普及や、飛行機で人が空を飛ぶことに挑戦して、生活に変化や
新たな知見を与えた、偉人たちのような大きな挑戦も、来週から起こされなくても、
自分で起きて会社にいくといった小さな挑戦も、挑戦の大小には関係なくその人本人や
周りの方々にとっては、新しい自分、新しい風景が広がっているのは同じだと思います
今、自分が人生の大一番を迎える挑戦をしていて、気づかされるのは
挑戦は、自己成長においてもですが、人生を豊かにするための貴重な機会だと思います
疲れ、立ち止まりそうになっているときの友人達の励ましや、支援は、これまでの自分が
生きて、示してきた姿勢を認めてもらえて、応援されているように感じて、それは背中を
押してもらって、また走りだせる力が湧いて活動ができます
実感として挑戦すること自体に価値(意味)があると思います
挑戦を通じて得た経験や学びは、必ず未来に活かされます
挑戦の先にあるものは、自分自身のなりたい自分であり、ありたい自分の姿だと思います
そしてそれはきっと自分だけではなく、関わってくれている皆さんに、小さくても
何らかの波紋や変化を与えるものと信じています
同じ志をもった仲間や家族と共に、またその想いを背負い、様々なことに挑戦して、
その先にある、新しい自分、新しい風景に出会いたいと思い、走り続けたいと思います
卒業、進学、就職・・今この時期に挑戦しようとしている方々が、
新しい自分に出会えますように応援しています